大工棟梁
都幾川木建(ときがわもっけん) 高橋俊和
1954 大阪市生まれ
1979 京都工芸繊維大学、京都府立大学社会福祉学科(中退)を経て、品川職業訓練校木工技術科修了。その後、家具工場、木工作家林二郎の工房「富国工芸」、障害者のための道具をつくる「でく工房」で修行。
1984 「棟梁に学ぶ家」グループに参加、三宅島で伝統構法を学ぶ
1990 高橋木造建築研究所開設
2006 都幾川木建に改称
1. 表紙
2. 木の魂が宿る家
3. 「結(ユイ)」で伝統構法を学ぶ
4. 中心軸のある家づくり
5. ギャラリー
インタビュー実施日時:2010年4月12日
於:都幾川木建(埼玉県ときがわ町)
聞き手:持留ヨハナエリザベート(職人がつくる木の家ネット)
2010年4月、埼玉県比企郡ときがわ町、都幾川木建の高橋俊和さんの自宅兼事務所をお訪ねして、お話をうかがいました。このあたりは西川材の供給地。建売住宅が無数に並ぶ東武越生線沿線の新興住宅地から外れるにつれて、針葉樹の植林地と建具屋さんの工場が増えてきます。小さな川をわたり、お寺への入り口の矢印を目当てに山手に入ると「都幾川木建」の看板が。なだらかな山の斜面に、作業場と自宅とが並んでいます。
童話的なただずまいと
外に貫通する巨大な梁

雑木林と植林地の入り交じった丘のひだにこじんまりとある山里。春先のしとしと雨に、芽吹いたばかりの木々の明るい淡い緑と山桜の白に近いピンク色が、乳白色の空をバックにほわっと煙っている。そう広くはない谷を右手の山側にのぼると「奥へ奥へと歩いて行くと、林の入り口に不思議な家が忽然とあらわれました」と、お話にでも登場しそうなただずまいで、高橋さんの家がある。お話といっても、日本の民話でなく、宮沢賢治の童話のような、ちょっとレトロで洋風な感じ。地面の傾斜をそのまま生かした石場建ての高床。妻側の上部が切り落とされた兜造りのかわいい屋根、灰色っぽい土壁の真壁に小ぶりな家の割には太く黒々とそびえる柱、木製建具の窓のリズミカルなデザイン。つくりとしては伝統構法なのだが、ひとつひとつの要素はそんな童話的な雰囲気を奏でている。
妻側の中央に庇のついた玄関口があり、門のように訪れる人を迎える太い二本の柱の間に、家に入る大きな扉がついている。その庇の上に、ピノキオの鼻、いや天狗の鼻のように巨大な梁がニョキっと突き出しているので、家の正面全体が大きな顔のようだ。その開いた口の中に足を踏み入れると、扉の向こうは、栂板貼りの土間の、吹き抜け空間だ。

家の中に入ったはずなのに、街路にいるような感覚に陥る。まるで「本当の家」がその街路に面して建っていて、その2階に木登りでもするような楽しい外階段と踊り場がとりつき、街路に面して広い濡れ縁がついているかのようだ。そしてその「本当の家」の額にあたるところからは、あの、庇の外まで貫通する太い、太い梁がズドン!と突き出している。その上を見上げれば、屋根裏の小屋組の木々が、縦横に走り、うねっている。ここは、太い枝を何本もつきだした大木の下に守られた街なのだ!
家の中心に大木が生えたような
太い大黒柱
土間から一段あがり、濡れ縁空間から、白い引き戸の向こうの「本当の家」へと歩みを進める。なんと、目の前の空間のど真ん中に、一瞬自分の目を疑うほどに太い木が生えているではないか。「この家のヌシはわしじゃ!」とでもいうように無言の深い存在感をたたえて。吸い寄せられるようにそばに行ってみると、それは中がウロになった古い巨木だった。
「この材に、出会ってしまったんですよ」と高橋さん。材というより、木そのものだ。「高野山に生えていた樹齢800年ぐらいの杉なんですけれど、このクラスの木が7本ぐらい、ウロが大きくなりすぎて、台風で倒れると危ないというので切ったうちの一本らしいんです。めぐりめぐって、つきあいのある岡部材木店(飯能市)に入ってきて『これ、何とか使ってくれない?』と言われてね。こんな太いの重いし、何をするのも大変ですから、困ったな〜とは思ったんですけれど、見てしまったら、もうどうにか使うしかないじゃないですか・・・」表面はゴツゴツしてはいるが、すべすべに磨かれて、手触りがいい。一年、一年と成長してきた木の、長く生きてきた最後の年の表面が現れていて、その手触りを通して、木の魂と交信できるような気持ちがする。
胴回りはおとなが2人かかっても手をつなげないほどの太さ。ウロの開口は下の方が開いていて、そこに縄ばしごが垂れ下がっている。はしごの下から、とっくの昔になくなった木の内部に入ることができる。見上げると、暗がりの真上に2階の光が見える、不思議な景色。「空洞になっててもね、これだけ外周のボリュームがあれば構造的には強いですよ。ここまで長く生きてきた木の尊厳を守れるように、材として細切れにしないで、大きいものを大きいまま使ってあげたい、というのが岡部材木店の仕入れ担当者の願いだったんです」
はしごをのぼると、ひょこっと2階に出る。このウロの巨木に、例の太い梁ががっちりとささっているのだということに気づく。差し口の近くには、シャチ栓が打ち込んであり、梁がのびていった先は、玄関の2本の柱をつなぐ梁がしっかりと受けている。家全体の中心に樹齢800年の杉が大黒柱としてどっしりとそびえ、その向かいに2本組みの柱が立ち、大黒柱との間を太い丑梁がつないで、この家の大きな空間をつくっているのだ。「玄関の外に突き出ている丑梁の先にはね、いずれ木彫で飾り彫りしようと思ってて、いつになるか分かりませんけど、楽しみにしてるんです。」と高橋さん。

生活文化同人の同人誌に寄せた「ご縁木物語」という短文で、高橋さんは建築当時のことをこうふりかえっている。「自宅の大黒柱は、直径1.5メートル、高さ4メートル、重さ1.8トンの、中が洞になった杉の老木で、縁あって高野山から運ばれたものですが、工事にあたっては基礎工事をすませた後、すぐに大黒柱を設置して周りに足場を組み、その場所でスミカケ、加工をしなければなりませんでした。足場に一人乗って牛梁が組み込まれる仕口を刻んでいると、自分が木にとまったキツツキかセミのような気がして不思議な錯覚に陥ってしまう時があります」
「表面から年輪を数えてちょうど400年あたりで年輪が詰まったところがあって、ノミをふるう度に水しぶきがとびました。400年前といえばちょうど秀吉の時代にあたりますが、今まさに400年間封印されてきたその時代の木の姿を玉手箱を開けるがごとくに切り開いているかと思うと、胸が熱くなるのを感じました。そして、いにしえの水を含んだ木の切りくずを、思わず口にして噛み締めました。ほろ苦い味と共にその時代、その木と時を越えて契りを結んだような気がしました。その時の大黒柱から出た木屑はゴミとして捨てることができず、今も袋に入れて保管しています」
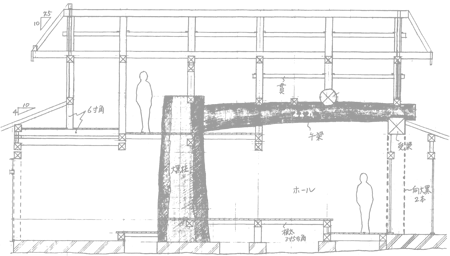
三宅島で学んだ伝統構法のやり方だ。
木が先にあって、家の形が決まってくる
単なる材料とはとても思えない

「我が家のようにここまで大きいと使いにくいんですよ。だから、誰も手を出さない。いやがります。はじめは抵抗感があったんですが、ここまで生きて来たのに、何とか活かせないかなあと、とうとうやる気になったんです。大工の常識からは大きくはずれたことでしたが、何とかそれを生かしたかった。建材として使われる杉、桧だけでなく、ヒマラヤ杉、ソロ、クリ、カシ等の、山から消えていっている広葉樹、雑木もこの家の床板、階段に使っています」
木との出会い、が先にあった、ということのようだ。「普通設計といえば、まずデザインがあって、それに合う材をどう集めようか、っていう話になるでしょう?ぼくは逆な場合が多い。素材に出会って、この縁を伝統構法の技術で、どう結んでいけるのかというところから入っていくんです。ただし、大きかったり個性的な木というのは流通している規格材と違って一筋縄ではいきません。難しい問題もたくさん経験してきたので、木の力、大自然にたいする畏怖の念は忘れないように肝に銘じています」
そんな高橋さんのもとには、木を愛するお施主さんが自然と集まってくる。施主自ら買い集めた木を使って家をつくってほしい、という人。知り合いのきこりさんに木を伐ってもらうところから家づくりを始めたい、という人…。高橋さんが大黒柱として使った、高野山の800年ものの木の幹のひとつ下の部分にあたる材は、そんなお施主さんの家の大黒柱になった。
「木を単なる材料とは思えないんです。木そのものがもっている何かがある。じつは私、その木や家になりきれるんですよ、気持ちや魂がね。理屈でなく、身体感覚で、木や家に同化してしまうところがあるんです。そうやって木の使い所をイメージする。夢の中で分かることもあります。ゆるやかに曲がった2本の木があって、その2本の間にブランコがかかってゆれているんです」不思議な木、イレギュラーな木を「使いにくい」とせず、つくり手の方から木に内在していって、どう使われたい木なのかを感じ取る、そんな流れでこの家は生まれたのであった。
木や家の時間は
人間の時間を越えている
「木も家もね、人間とは違うスケールの時間のものなんですよ」高橋さんの家の大黒柱になった木のいのちの長さは、想像をはるかに越えている。百年もつ家をつくったとしたら、その家に将来誰が住むことになるのか、思いもよらない。「百年を越すようになると、木も家も数奇な運命をたどります。だから、うちでつくる家は、どんな運命をもたどれるようにと意識しています」
高橋さん夫婦に子どもはない。この家も将来誰がどう住むのか、考えの及びようがない。「どんな方の手に渡るのか分からない。だからこそ、個人の嗜好や都合でなく、木のいのちに寄り添って、後の世の人が『これは壊せないな』と思う家をつくりたいのです」
家は個人の財産。けれど、木や家が人間の寿命より長いとしたら、家は自分のものであって、そうでない。家は残り、町並みの顔となる。当初と違うライフスタイルの器ともなりえる。住み継がれていく家は、それだけの力をもっているということだ。「伝統構法は長寿命の家づくり」ということは、よく言われる。長寿命ということを本当に意識してつくれば、そこには「人間が考える」以上の、違った発想が自ずとたちあらわれてくるはずなのだ。高橋さんは木の声に耳をかたむけるようにしてつくっているのだろう。
国では「長期優良住宅」政策を推し進めている。住宅の履歴の保持、メンテナンスのしやすさ、省エネ性能、耐震性能などが、長期優良住宅の基準として並ぶ。しかしそれ以前に、家自身が奥深さ、いのちをもっていてはじめて、真に長く残っていくのではないだろうか。







