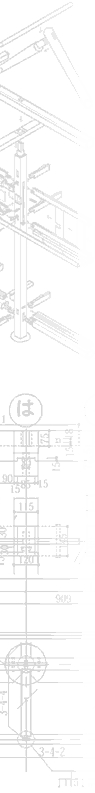
■「外回りの建具」と「内で仕切る建具」
さて、これまで2回の「そもそも話」で、そもそも日本の木の家は林立する柱を軸組みとして、その上に屋根がかかる「柱の家」であること。柱間を壁にすることも、開放しておくことも自由自在で、時に応じて開け閉めできる建具が工夫されてきた、ということまで、お話ししてきました。
さて、建具には、風雨、明るさ、暑さや寒さなどの外部環境を遮断したり取り入れたりする「外回りの建具」と、部屋と部屋とを必要に応じてつなげたり隔てたりする「内で仕切る建具」とがあります。「外まわり」の建具には、頑丈な板や軽くても強いアルミでできた「雨戸」、軽い木の骨組みに紙を貼った「明かり障子」、紙のかわりにガラスをはめ込んだ「ガラス障子」などが、「内で仕切る建具」には「襖」などがあります。

■建具のルーツは平安貴族の調度品にあった!
みなさん、百人一首の絵札の柄をおぼえておいででしょう。布や紙でできた華麗なスクリーンやカーテンを身の回りに巡らせ、身分に相応しい装束に身を包み、格式に合った小さな畳に座った平安貴族の姿が描かれていますよね? 平安貴族は、壁のない、大きなワンルームのような空間を、几帳や衝立、屏風などで仕切ったり囲ったりして、自分の居場所や寝る場所をつくっていました。調度品を小道具、装束を舞台衣装として用いて、その人の存在や雰囲気を「演出」していたのです。
建具の多くの起源は、この平安貴族の調度品に求められます。今でも夏の暑い時期には、巻き上げ式の簾をさげて用いますが、そっくりなものが平安時代の絵巻物にも見られます。また、衝立や屏風も、茶室や料亭をはじめ、座敷のある居酒屋やそばやでも、よく使われています。襖や障子は、もともと平安時代には置き道具であったのが、敷居と鴨居の間に取り付けるという工夫により、スライドして使うことのできる常設の建具となっていったものです。引き違いの建具が、建物の一部として定着していったのは、武士の時代になってからということです。

■障子や襖はいつからあるの?
今でこそ障子といえば、華奢な木の骨組みに和紙を張ったものと同義ですが、かつては「ものとものとを遮る」ための調度品や建具は、みな障子と呼ばれていました。さしさわりがあることを「支障がある」といいますが、その「障」の字の用例といっしょです。今で言う障子は明かりを採り入れるから「明かり障子」、ひとつの空間を手前の部屋と奥の部屋とに仕切る襖は「襖障子」です。どちらも衝立式、立て掛け式のものが平安貴族の時代からあり、つづく武士の時代には、寺社や武家屋敷にも常設建具となって定着します。
一般の民家に襖が普及するのは江戸末期頃ではないかと思われます。民家にはもともとワンルーム的で、土間以外の高床空間は板の間続きであることが多かったようです。夫婦の寝所とあらたまった接客をする畳敷きの座敷まわりには、仕切る建具を用いたようです。唐紙を貼った装飾的な襖を使うのは座敷との境に限られ、それ以外の間仕切りとしては板戸が一般的だったようです。座敷がないような家にはもちろん、襖もなかったのです。和室が少なくなった今、「襖は押し入れの目隠し」ぐらいにしか思われていない節もありますが、庶民にとって襖とは、贅沢な建具だったのです。
明かり障子が一般庶民の間にも手の届くものとなったのは、江戸中期から明治にかけてのことでした。軒の深い日本の木の家は、昼でも室内は暗いもの。それが外回りに明かり障子をたてると、全面が白くほんのりと明るんで、部屋がやわらかい光に満たされるのです。張り替えたばかりの真っ白な障子は、気分も新たにしてくれます。古谷綱武の「白い障子のある家」というエッセイに、明治時代に富山から北海道に開拓で渡った人が「成功して暮らしが楽になったら、まず白い障子のある家に住みたいね」と語る話がでてきます。明かり障子が千年も前からあったとはいえ、庶民にとっては丈夫で白い和紙は高価なものだったでしょう。「眼にしみるような美しい白い障子を楽しむことができたのは地主だけで、富山県の長い冬を、彼らは板戸を閉めきった薄暗さの中で暮らす以外になかったのだ」と文章は続きます。電灯が普及していない頃は「白い障子」のもたらすほの明るさは庶民の憧れだったのです。






