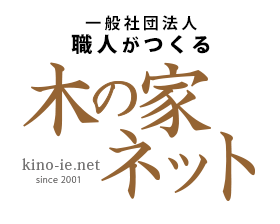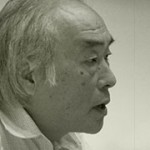車で栃木市に隣接する佐野市の葛生町の「広瀬染物店」の店舗併用住宅の建設現場へと向かう。葛生には、2億5000万年前のサンゴ虫類や紡錘虫類など、海棲生物が堆積してできた生物由来の石灰の鉱床があり、この石灰を原料とした「漆喰」の産地として有名なところだ。



広瀬染物店は、お祭りの半纏や暖簾などを受注して染めるお店。お客様とのやりとりの中で仕事が進む。「新しく建つ店舗は、染め見本などを並べるだけでなく、人が集えるギャラリーやイベントスペースとしても活用したい」というのが店主の広瀬さんの夢だ。
「葛生産の漆喰をふんだんに使い、染め物店らしい、小粋な趣味性を感じさせる数寄家づくりを提案いたしました」と山本さん。丸太の縁桁と軒裏の華奢で繊細な構成、純白の美しい漆喰壁。若い頃から京都の有名工務店で開く勉強会などにも通い、数寄家を得意とする山本さんの腕のふるいどころだ。
「お施主さんの依頼の範囲内だけにとどまらず、期待や想像を上回る提案をしてさしあげて、喜ばれる。そんな仕事を心がけています」と、山本さん。「思い描いていたより、ずっとよくなりそうで、楽しみです!」と広瀬さん。二人とも満面の笑顔だ。広瀬さんは建築の過程そのものをとても楽しんでいて「漆喰塗り壁の家建築中!」と店の前にも貼り紙を出している。お施主さん自らが、大兵工務店の口コミ宣伝をしてくれているのだ。
「数寄家」が山本さんのもっている大工技術のひとつの極みとすると、そのもう一端を担うのが、宮大工の技術だ。仕口・継手や隅木の接合部、社寺建築の美しい屋根の勾配など、複雑に組み合う接合部や曲線を、曲尺一本で巧みに作り上げていく「規矩術」が宮大工の技術の中核をなす。



「経験は随分積んできましたが、それだけでは、足りない。きちんと勉強せねば、と、50代になってから、日本伝統建築技術保存会の伝統建築技術養成研修を受講し、認定試験も受けました。一生勉強です」という山本さん。社寺や宇都宮城だけでなく、一般の住宅にも規矩術を応用した納まりが随所に見られる。
栃木市郊外で施工中の平屋の住宅の現場で「いちばん苦労したところは?」と訊くと、建物の隅を見上げてこう教えてくれた。「隅木はむずかしいんです。ここがピタッと合っていて、直角がキッチリと出ていないと、建物全体が歪んでしまいますから」
しかし、数寄家、宮大工いずれの技術にしても、その大本となっているのは「木を活かす」心だ。数寄家で見上げた軒裏にしても、流れるような神社の屋根の曲線にしても、木そのものの表情や力強さを活かすための技術なのだ。
「家に一歩足を踏み入れ、玄関に立った時に、木がどう見えるか。その構成をどうつくるかを、大切にしています」と山本さん。施主はそうは頼むわけではないが、どの材料のどの部分をどのように見せるかを、常に考えている。それは図面には書き表せないことだ。木を選び、配材し、加工する大工棟梁の頭の中でのみ構成されることなのだ。