前回、木の家ネットの若手大工さんたちが中心となって建て、いま、愛・地球博で公開されている「サツキとメイの家」を通して、職人がつくる木の家の魅力をご紹介しました。ところが「サツキとメイの家」のような木の家らしい家が建てられることは、今では少なくなっています。少なくとも都市部でその傾向が大きそうです。・・・なぜだと思いますか?
「そういう家は地震に弱いからじゃない?」「準防火地域じゃ建てられないし」などと思われる方もあるでしょう。 特に、阪神大震災、そして昨年の新潟中越地震などの折りに「古い木の家は弱い」という報道が数多くあったように思われます。本当にそうなのでしょうか?(木の家ネットメンバー有志による新潟中越地震の被災地での調査・住宅相談を通じて分かったことをレポートしています。また木造住宅の防火性能については「火の用心1,2」にてまとめていますので、ご覧ください)
地震への備えは安全性を考えた場合に家づくりにとって大きな課題です。古い家は本当に地震に弱いのだろうか?ということがようやく検証されるようになってきました。なぜ「ようやく」なのか? どのようなことが検証されているのか? などについて、さる5/15に木の建築フォラムで行われた「木の力を探る?構造編?」での木造実験・七賢連続発表会の報告も兼ねて、お伝えします。
■建築基準法は昔ながらの日本の木の家を対象にしていない?
地震などの災害被害を最小限におさえることが、家をつくるにあたっての最低の技術基準を示した「建築基準法」の大きな役割です。また、住宅を建てる人に建設資金を融資している「住宅金融公庫」(平成18年度末までに独立行政法人へ変わる予定)では、その融資にあたって満たさなければいけない具体的な仕様を決めています。そこでうたわれているのは「定められた量の壁をつくること」「筋交いや合板などで強い壁をつくるのがのぞましい」「木と木の接合部は金物で補強」などです。そのような造り方が、今の木造住宅を造るときの基本的な考え方となっているようです。
「サツキとメイの家」のように貫や土壁を使った造りとはだいぶ違う造りですね。昔の家は今の家とくらべると開口部の多い開放的なつくりで、土壁があるところでは筋交いなどは入れず、合板などの木質建材も登場しておらず、木と木の接合部は仕口や継ぎ手といって大工が高い技能で細工した木組みです。建築基準法や住宅金融公庫の仕様は、大工たちがそれまでずっとつくってきた家を対象にしていないのでしょうか?
■西洋の建築学に学んだ人たちが、法律をつくってきた
このなぞを解くために、日本の家づくりと、家づくりを取り巻く法律の流れを少しさかのぼってみましょう。家づくりは、その地元の大工棟梁がになってきたことはご存知のとおりです。どのような家づくりをするのかは、地震に対する構え方も含め、大工から大工へと継承されてきました。一方、家づくりのきまりを作ったのは、国、具体的には、行政の立場にいる人たちです。彼らは大工に聞いて作ったわけではありません。明治時代に、できたばかりの大学の建築学科に教えに来たお雇い技師に学び、西洋の建築学の考え方を基に作られたといえそうです。
西洋の建築学には「三角形は四角形よりも変形しにくいかたち(三角形不変の理)」という「トラス」という考えがあります。西洋の木造では、壁や床、小屋組などを歪みにくくするために筋交いや火打、方杖という「斜め材」を要所要所に入れます。柱や梁、梁と梁などが取り合う部分に三角形をかたちづくることによって骨組みが固まるような作り方します。三角形はその頂点をしっかりと作ってあげられれば力学的に骨組みを効果的に固めることが可能になります。比較的細い材料でもトラスを組むことで、小屋組でも大きな梁間を掛けることも可能です。
一方、棟梁たちがつくってきた日本の家は、西洋の建築学から見ると、理解しがたいもののようでした。「壁に筋交いがない」「小屋組を力学的に強くする斜め材が入っていない」「軸組に対して屋根が重すぎる」などなど。お雇い技師として日本の大学に初めての建築学科をひらいたコンドル博士は「普通の日本の建家は柱と柱の間が非常に明いて(原文ママ)居って、上に重たい梁が載っている。これらの大梁は細長い手弱き柱に差し合わせてあるのです(中略)木造家屋の全体に筋交いを入れ、三角形に致し、いずれの部分も変形せぬように作らなければなりません」と述べています。日本の家は非耐震的である、だから「より強くしなくてはならない」のだ、と。
■トラスを用いてこなかった日本の大工技術
日本の大工技術にはトラスという考え方はなく、斜め材を入れることもほとんどしてきませんでした。 タテに柱。ヨコに梁や桁、差し鴨居、足固めで四角の軸組をつくり、それぞれの部材が取り合う接合は精度の高い仕口や継ぎ手を作ってきました。柱と柱の間には障子や板戸といった建具を入れて開口部としました。壁にする場合には、貫と呼ばれる横材を通し、それに竹で小舞を掻いて土を塗る、あるいは板を落とし込んだり、打ち付けたりしていました。重たい屋根も、梁を何段にも交差させながら重ねあわせて小屋組をつくるなどして支えてきました。
棟梁たちは斜め材で三角形をつくって固めるということはしてこなかったようです。比較的太い材料が入手しやすく材が柔らかい針葉樹であったこと、その加工しやすさや道具の使い方による考え方、職人の美意識などなど考えられるかもしれませんが、どうしてそうだったのかはよく分かりません。補修などで、斜め材を用いて補強していたものなどはいくつかあるようですが、基本的に斜め材で固めるということはしてきませんでした。柱と梁で四角形に組まれた接合部には金物などによる補強も必要なかったのです。その仕口継ぎ手に対しては、当時の、「日本の住宅はお粗末」と言い切っていたお雇い外人技師でさえ「仕口は最高の精度で作られている」と感嘆しています。
金物で接合部を補強し緊結するのではなく、一方に穴を開けそこにホゾを差込み込み栓で留める(差仕口といいます)。あるいは、切り欠いた同士を精度よく組み合わせて固める(組み手)。そのような作り方で接合部を考えていました。あくまでも木の特徴を読みながら、木と木の関係で接合させる仕組みです。穴をあけたり、切り欠いたりするのですから、それなりに太い材料も必要になります。差鴨居が三方や四方から差し込まれる大黒柱がそれなりに太さが必要であったのもそいうった理由があったわけです。
しかし、力の掛かる柱を切り欠くということは、西洋の建築学の常識からいったら、考えられないことでした。「なぜそれよりもトラスをつくらないのか? 金物でしっかり補強しないのか?」 西洋の建築学の目からは、日本の木組の家は理解しがたいものだったのです。だからといって、日本の古くからの大工技術が建築学科で技術として工学的に検証されることは、ほとんどありませんでした。その頃は、西洋からの建築学が最先端の技術だったので、なぜそうなのか?ということを研究対象にする人すらいなかったのですね。ということで、明治時代に大学の建築学科が創立されて以来、日本の大工技術は「古いもので理解しがたいもの」として、ごく最近まで、無視され続けてきたのです。
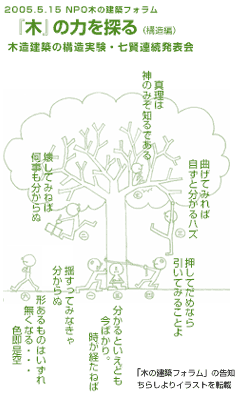

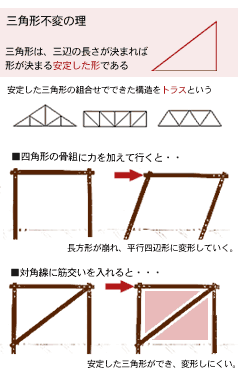
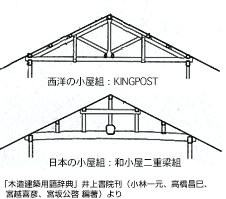
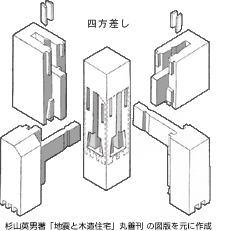
「サツキとメイとあなたの家」はこちら






