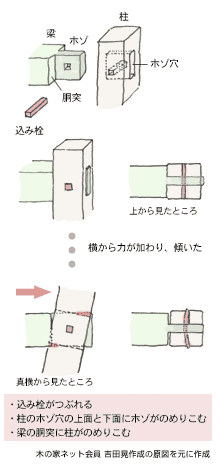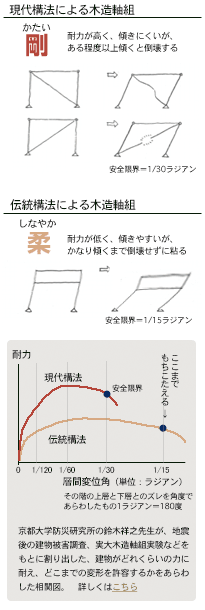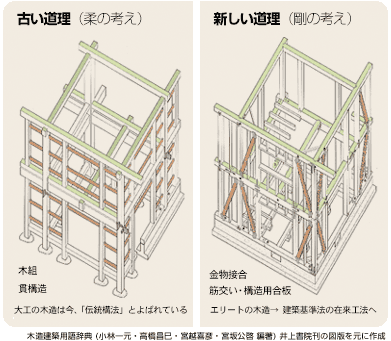■昔ながらの日本の家の地震に対するふるまい
では、「三角形」をつくらなかった日本の木の家は、地震などの力に対してどうふるまうのでしょうか?
力を受けると、四角形を構成するタテとヨコの骨組みは、そのぶつかり合っているところがつぶれて(めり込み)いきます。そうすると四角形は菱形の状態になっていきます。このときにそれぞれの接合部で込み栓や楔が頑張っていれば、それが抜けずにズルズルと菱形が押しつぶされてひしゃげていきます。このズルズルと菱形に押しつぶされていくことが力のエネルギーを吸収していることになっているのです。
四角形の骨組みの中に、めり込みを起す接点がおおければ多いほどエネルギーの吸収する量も増えますので、それだけ壁の性能としては高いといえます。柱の間に貫を通すのもそういった効果があるからです。「大工がきちんとした仕事をしていた家であれば、大概の地震では軸組はひしゃげてももとに戻る」というのが日本の大工技術の考え方でした。つまり、「ひしゃげないようにトラスで固くつくる」西洋の技術と比べると、「ある程度ひしゃげてももとに復元するようにつくる」日本の大工技術は柔らかい構造だといえます。力に対して固く抵抗するのではなく、力をやんわりと受け止め、粘り強くしなやかに力をかわそうという仕組みなのです。
めりこみが起き得るのは、接合部が木と木だからです。これが木と金物だったりすると、金物の力の方が強く、木だけが一方的にめり込み、変形が大きくなったり、局所的に破壊がおきるおそれがあります。また、柱と梁が幾重にも重層する結果として、家全体が編んだかごのようになっていて、エネルギーをやんわりと吸収するポイントがいくつもできています。これも受けた力をうまく分散させるしくみとして機能します。(このことを「総持ち」といいます)木の特性をうまく活かした木組みの家だからこそ「やんわりと受け止め、粘り強くしなやかに力をかわす」ということが実現できるのです。
■西洋流の建て方への移行の提言、提言を受け入れなかった大工棟梁
西洋の建築学の剛の論理からみれば「考えられない非耐震性」としかとらえられないことが、地震国日本では大工技術としてずっと伝えられて来たのです。お雇い外人技師が教鞭をとる日本の大学の建築学科が初めて卒業生を世に送り出したのは明治12年のことでした。その12年後に濃尾地震が起き、木造家屋の約14万戸が全壊、約8万戸が半壊するという大きな被害を受けました。コンドル博士の教え子として日本の建築行政をになっていく立場にあったある卒業生は次のように提言しています。「貫は全廃し、六尺以内ごとに柱を建て、そのあいだに筋交いと間柱を入れたし」「柱の根の勝手次第に動くのを防がなければならない」これは、大工棟梁が伝承してきた建て方をやめ、西洋流の建て方に移行しようというよびかけにほかなりませんでした。
大工棟梁たちはこのような提言を受け入れたかというと、ほとんど受け入れることはなく、伝承されてきた大工技術を使い続けて行きます。一方、建築行政をになっていった役人たちが関わる木造の建物(主に学校、駅舎などの公共建築物)では、西洋流のトラス技術が採用されていくようになります。
大正時代に、剛構造を唱え、関東大震災後に「市街地建物法」をつくることに尽力した佐野利器という東京大学の教授に対し、海軍技師真島健三郎は、上野谷中の五重塔が関東大震災でも倒れなかったのを例に挙げ柔構造を唱えるといった「剛柔論争」もあったようですが、当時、地震波と建物の揺れ方との関係を解明するには実例が少なく、論争は曖昧なまま終わったそうです。海軍技師という当時の最先端の技術者が柔構造という投げかけをしたというのは、面白いことですね。
■「エリートの木造」の流れを汲む建築基準法
以上のような事情から、日本には「大工の木造」と「エリートの木造」という二つのまったく違う技術が混在するようになったのです。西洋流の剛の考え方を学んだ「エリートの木造」を代表する昭和初期の研究者である田辺平学は、壁がないのが日本の建物が地震に弱い原因だとし、のちの建築基準法の壁倍率の考え方の基礎を築きました。
しかしながら「エリートの木造」は普通の人が住む民家レベルにまではなかなか浸透していきませんでした。第二次大戦前までには、それを浸透させていくだけの強制力をもつ仕組みがなかったからです。「それではいけない、これから建てられる家はすべて、国民が文化的な生活を送るための最低限の基準を守っていないと」ということで、「エリートの木造」の考えを下敷きにして戦後にできたのが建築基準法であり、住宅金融公庫の仕様へつながっていきます。つまり、建築基準法や住宅金融公庫の仕様は、大工の木造の流れでなく、エリートの木造の流れの延長上にあるものといえるでしょう。
■「古い道理(柔の考え)」と「新しい道理(剛の考え)」ができてしまった・・
話が長くなりましたが、「サツキとメイの家」で見るような「昔ながらの日本の木の家」は、やんわりと力をうけとめる柔の考えにもとづく、大工棟梁たちが綿々と伝えて来た「大工の木造」の流れにあります。これを木の家ネットでは「古い道理」と震災レポートの中で名付けました。それに対して、強くかたい構造をつくることで力に耐えようとする剛の考えにもとづく「エリートの木造」の流れをくんだ建築基準法や住宅金融公庫の仕様に規定される木造のことは「新しい道理」と呼びました。新しい道理が法律や融資条件の仕様として強制力をもつようになってくると、伝承されてきた「古い道理」である日本のすぐれた大工技術は途切れていってしまいます。「昔ながらの技術をもった大工さんなんて、まだいるの?」「サツキとメイの家は昔なつかしい過去のもの」という状況が生まれているのです。
注:基準法や公庫仕様では必ずしも、昔ながらの大工技術を否定してはいません。しかし、最低基準である条文等が優先されてしまうために、すぐれた技術であってもそれを現実的に評価しにくい状況があるようです