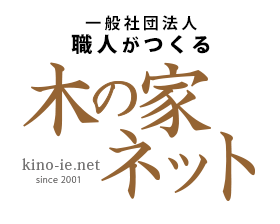林業経営のスタイルはさまざま
よ ところでミドリちゃんのところは、林業の規模として、大きな方なのかい?
ミ ウチなんか全然ですよ。70haくらいしかありませんし。
よ 立ち入ったことを聞くようだが、そのくらいの面積だと経営の方はどうなんだい?
ミ う?ん、まあ楽ではないです。幸い、ウチはきょう見ていただいたような良い山が比較的ある方なので、何とかやってますけど、それでも木材だけだと厳しいというのが正直なところです。
よ あれ、何か副業もやってたんだっけか?
楠 何言ってんだよ、親方。いつも立派な干し椎茸をもらってるでしょ。あれだってミドリちゃんちで作ってるんだぜ。
よ ああそうか。
ミ 椎茸も輸入品が多くて楽じゃないんですけどね。あと、ウチでは山菜やその加工品なんかも作っていて、道の駅や直売所で販売してます。この収入も大きいんですよ。もっともそっちの方は祖父母や母が主力で、私はあまり手伝っていないんですけど。
よ ふーん、いろいろやってるんだなあ。
ミ ウチは専業林家ですけど、林業って本当に幅が広いなって思うんです。山を手入れして、椎茸や山菜も販売して、そうやってさまざまな山の恵みを生かしながらこの地域で暮らしている、それがウチにとっての林業なんです。
楠 いわゆる「自伐林家」(持ち山の手入れや伐採といった現場作業に自ら携わる林家のこと)という人たちはそういう経営スタイルが多いよね。
よ なるほどねえ。林業って言うと木を売って食べてるってイメージがあるけど、いろいろなんだな。
楠 もちろん木材だけでやってる人もいるけどね。でもそれにはある程度の規模が必要だし、昔ならともかく丸太の価格がこれほど安いんだから「大規模山林所有者」って言われる人たちも苦しいと思うよ。
ミ ウチくらいの所有面積だったら、会社勤めや農業との兼業という人もけっこういますよ。林業だけだと厳しいですから。
よ よく日本の山は所有規模が零細だって言うよな。林家の7割だか8割は所有面積が5haにも満たないって聞いたことがあるぞ。そんな人たちはどうしてるんだろう?
ミ そういう人たちは林家というより、農家だったり、普通のサラリーマンだったりで、山の管理は森林組合や林業会社に任せているというのがほとんどです。
よ よ:ふーん、山持ちさんもいろいろなんだな。
森林所有者のイニシアチブをどう確保するか
よ 林業のスタイルがいろいろだっていうのはわかったが、いま国がやろうとしている林業改革の方はどうなんだい?
楠 「森林・林業再生プラン」(前回の林材レポートを参照)のことだよね。小規模な林地を取りまとめて効率的な経営を実現しようっていうのが眼目かな。いわゆる「集約化」ってやつだよね。それと作業道の整備。これが今回の改革の二本柱だね。
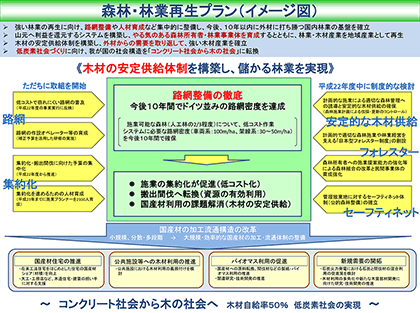
よ それで林業は本当に元気になるのかい?
楠 国産の木が売れる機会は増えると思うよ。集約化で規模が拡大すれば、ある程度効率化も進んで木材が安定して生産されるようになるだろうし、需要の方は最近は大手ハウスメーカーでも国産材を使おうって真剣に考えてるみたいだから、ある程度は期待できるだろうしね。
よ 最近じゃ合板業界も国産材にご執心だしな。
楠 あれ? ふだん合板なんか使ってないのによく知ってるね。
よ それくらい知ってらい。だがよ、そうやって国産の木が売れるってことなら、再生プランもうまくいきそうじゃねえか。
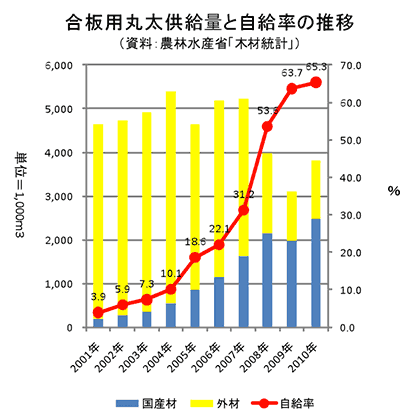
楠 でも今回の改革では価格対策は何も打ち出されていないんだよね。経費を下げて、その分、利益を浮かそうって発想なんだけど、値段が下がっちゃったら元も子もないでしょ。それに集約化っていうけど、ミドリちゃんたちみたいな中規模の自伐林家をどうするかという問題もあるし。
ミ ウチは70haを持ってるとはいえ、1カ所にまとまってるわけではないので、ひとつひとつの規模は小さいんですよね。幸い主力の林地は30ha以上のまとまりがあるので、施業計画を立てて補助金の優遇も受けられたんですけど、新しい制度にどう対応しようか、まだ決めかねてるんです。

よ なんだい、その施業計画ってやつは?
楠 所有者が自分の山をどうやって経営するかの計画を立てて認定してもらう仕組みがあるんだよ。認定されれば補助金がかさ上げされたり、所得税や法人税の特例も受けられるから、意欲的な林家の多くは施業計画を立ててるはずだよ。ただ、計画の対象になる森は30ha以上という条件があるから、対応できない人も多いんだよね。
ミ ウチでもその面積に満たない山があるので、隣りの人と共同で計画を立てたりしてますけど、それがうまくいかないところは計画なしで経営してきたんです。優遇措置は受けられないとはいえ、補助金は使えるので。ただ、新しい政策では、計画制度が改革されて、面積の条件がもっと大きくなると聞いてますし、今後は計画を立てなければ補助金が使えなくなるらしいので、どうしようか、迷ってるんですよ。
楠 名前も森林施業計画から「森林経営計画」に変わるんだよね。計画が立てられた山だけに補助金を出すことにして、集約化を一気に進めようというのが政府の青写真なわけだ。
よ つまりはどうしても規模拡大をしろって迫られてるわけだな。
ミ 仕方がないから地域で相談して計画は共同で立てようかって話はしています。でも、個々の所有者が自分の持ち山を独自の方針で経営することができるのかどうか、そのあたりがよくわからないので困ってるんです。
楠 計画を立てるときには森林組合に協力してもらうんでしょ。
ミ 計画自体は森林組合が立てる形になるかもしれません。
楠 だったら、組合とよく相談しておく必要があるね。計画は共同で立てるけど、自分の山は自分でやるから、そういう配慮をしてくれって。
ミ この地域は規模が小さくても他の仕事もしながら山を一生懸命やってる林家が多いんです。組合もそういう事情はわかってくれていて、所有者のイニシアチブが確保されるような内容の計画を立てようと言ってはくれています。
楠 ここの森林組合はしっかりしてるからな。でもほかの地区はどうかなあ。新しい制度を杓子定規に推進することばかり考えてたら、所有者の意思が反映されなくなる可能性もあるだろうな。

よ どういうことだい?
楠 つまり、経営計画で集約化された山を組合なり林業会社なりが一手に引き受けて経営するようにするわけさ。
よ なるほど、そりゃあそれで効率が上がりそうだな。
楠 うん、政府が目指してるのもその形なんだよね。たしかに、山に思い入れがあまりなくて、単体では経営にまでは至らない所有者の山は集約化していった方がいいんだろうけれど、逆に山に思い入れのある所有者が自分の山に関われなくなるケースだって出てきちゃうでしょ。この地域みたいに所有者に意欲がある場合はそれじゃあまずいよね。だから今回の改革は、地域事情を踏まえた形で新しい制度を利用できるかどうかにかかってると思うな。
ミ 私たちもそう思って、この地域でひとつのモデルを示そうとは思ってるんです。計画は共同で立てるけど、自分の山はそれぞれが面倒を見てしっかりやっていけるようにしようって。
よ そうか、ミドリちゃん、がんばれよ。
ミ はい。