上/幾度も折り返し鍛えられた結果、 地肌に浮かび上がる美しい墨流しの文様
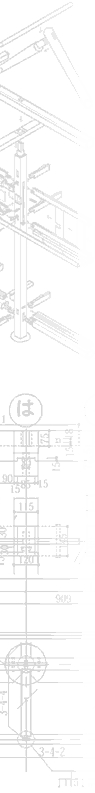
■「よく切れて」「刃こぼれしない」火造りの技
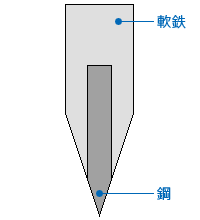
外国の刃物や今の日本で普通に量産されている刃物は、ほとんどが硬い鋼を型で抜いてグラインダーで削り出してつくります。これを型抜き刃物と言います。鋼だけでつくると最初はよく切れるのですが、刃が減るにつれて研ぎにくくなり、硬いだけに次第に刃こぼれしやすくなってきます。 それに対し鍛冶屋さんがつくる打ち刃物は、柔らかい地金と硬い鋼をあわせ、熱をかけて赤らめ、叩いて形成してつくります。赤らめ、叩いてつくることを「火造り」といい、火造りした刃物を「打ち刃物」「鍛造刃物」と言います。(西洋にもごくわずかではありますが、鍛造刃物もあります。ただし、鋼だけでつくり、やわらかい地金と合わせることはしません)鋼と地金を火造りして合わせることによって、鋼の切れやすさと地金の研ぎやすさを合わせもつのが、日本の刃物のすぐれた特徴なのです。 2005年1月に東京で行われた木の家ネット総会の解散後、大工さんたち数人と火造りの打ち刃物の技術を今でも実践している江戸鍛冶の左久作(ひだりひささく)さんを訪ねました。久作さんの仕事場は月島にあります。もんじゃ焼きが並ぶ通りの歩道からガラス戸をあければ、すぐそこに火が焚かれた鍛冶場が。久作さんの息子で、鍛冶職を継ぎたくて勤めた商社をやめ、火造りに励まれる喬作さんにお話をうかがいました。

■研ぎやすさをうけもつ「和鉄」ずっと昔につくられた製品を融かして使っている

和鉄の材料
「鋼と合わせる地金には、明治以前にタタラ製鉄法という砂鉄から低温でつくる製鉄技術でつくられた「和鉄」を用います。現代の高温でする製鉄ではこれは得られませんので、蔵の釘、お寺の扉の錺(かざり)金物など、昔の鉄を得て、溶かして使っています。古い鉄の入手は解体屋さん経由。350年前ぐらいのものからストックしています。グラインダーにかけて出る火花を見るだけで炭素分がどのくらいでいつ頃つくられたものか、大体分かりますよ。」 「和鉄は現代の製法でつくられる極軟鉄よりもさらに軟らかく、砥石当たりがもっともいいですね。和鉄の次に軟らかいのが、和鉄と同時代、欧米で岩鉄からこれも低温でつくられた軟鉄です。当時の線路や鉄橋に使われていたものを輸入して使っています。研ぎやすい刃物をつくるのに欠かせない材料である和鉄や軟鉄。遠い昔につくられたものに頼らざるを得ないのは、低温での軟らかい鉄づくりが量産に向かないからです。」
■和鉄に合わせられる「安来鋼」はいまや世界で一カ所でしかつくられていない
「地金の和鉄と合わせる鋼にも、タタラ製鉄法(和鋼ミュージアムのサイトをご参照ください)に近い方法でつくった「和鋼」を使います。日本で最後までこの製鉄法を守ってきた島根の安来の雲伯鉄鋼合資会社を日立金属が吸収し、今では「日立金属安来鋼」として生産しています。今となっては日本で唯一の和鋼ですが、日本各地の鍛冶たちは、例外なくこの安来鋼を使って刃物を鍛えていますよ。」 喬作さんと大工さんたちが話していると「鋼は青紙です」などという言葉が聞こえてきます。同じ安来鋼も炭素以外の不純物の配合具合によって、「青紙」「白紙」「黄紙」など、いろいろな種類に区別されるのです。不純物を取り除いた純粋な形に近い炭素鋼が「白紙」、それにタングステンとクロムを添加して硬度を増した合金鋼が「青紙」と呼ばれ、。切れ味、研ぎやすさなどがそれぞれ違います。地鉄との相性や道具に求める性能などによって、使い分けているとのことです。和鋼の以外にも、モリブデン、超特殊鋼などを用いることもあります。」
■日本の大工道具をつくる技術が続いていくには、つくり手が道具を使って行くしかない!
研ぎ、切れ味どちらをとっても優れた性質をもった日本の刃物が、その原料を今はもうつくられていない和鉄や、たった一社でしか作られていない安来鋼に依存している。火造りの技も量産に向かないということで継ぐ人はごくわずか。そのために日本のすぐれた鍛冶職人の技が消えて行こうとしています。 「欠けたらいけない、割れたらいけない、切れなあかん、それを全部満たすような刃物をすごい努力してつくってる。こんなすぐれた技術がありながら、継ぐ人が少なく、今やってはる人たちがいなくなったら、おしまいやろうな、という風前の灯火状態なんですわ。自分の仕事は道具をつくる鍛冶職の方たちに支えられているのに、と思うとそれこそ死活問題です。だから、ちゃんとした鍛冶職人がつくったいい道具を、機会があれば直接職人さんを訪ねて買うようにしてます。」と、このそもそも話に載せた打ち刃物を見せてくれた大工さんは言います。 鍛冶職人がつくるいい刃物で大工のいい仕事ができ、いい刃物を求める大工がいて鍛冶職人がものづくりをし続けられるのです。ホームセンターや金物屋でなく、大工が鍛冶職人から直接道具を買う時代があったのです。数多の名工がすぐれた鍛冶屋の道具をこぞって求めたといいます。刃物をあつらえた大工に使い勝手を訊くことで、鍛冶職人もさらなる創意工夫を重ねたことでしょう。あつらえた刃物が切れない時は大工は刃物を鍛冶職人に叩き返したものだ、という話も聞きます。両者の間の切磋琢磨がすぐれた打ち刃物と、すぐれた建築を生んだのです。 すぐれた刃物は一生ものといわれます。それがいいものであればあるほど、消耗品とはいえない財産になります。火造りの打ち刃物の値段が既製品の打ち抜き刃物よりも数倍高くても、使い勝手や寿命を考えれば、さほど高価ではないのです。しかし、もちがいいということを裏返せば、頻繁に買い替えるものでもない、ということでもあります。ひとりの鍛冶屋に対して何人かの大工が刃物をあつらえないと、鍛冶屋は成り立たない、のです。
■ 中央区のサイトで、区内の伝統技術に携わる職人を紹介する特集記事にインタビュー映像が紹介されています。
伝統技術
工芸編11:月島「刃物 左久作」
■ 左久作さんのサイトもご覧ください。
http://www1.odn.ne.jp/hidari/

職人がつくる木の家づくりの技術は、それを望んで頼んでくれる施主がいてはじめて、次の世代につながっていくものです。日本の打ち刃物の技術も同じことです。手の道具を大事に考え、鍛冶職人がつくる道具を使う大工がいてこそ、残って行くものですし、大工のすぐれた仕事も大工の手の延長となっていい仕事をする道具があってこそ実現できるものなのです。なかなか見えにくいのですが、木の家づくりを支える、どれが欠けても困るという職種はほんとうにたくさんあるのです。すぐれた刃物の価値がより多くの大工に知られることで、この環がずっと続いていくことを期待しています。一度切れてしまったら、もう二度と戻らない環なのですから。






