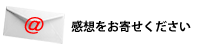阪神・淡路大震災発生から15年
自分の足で歩いて、見て思ったこと
1995年におきた阪神・淡路大震災から、もう15年も経ったのかとびっくりするぐらい、昨日のように印象強いのですが、当時私は大工を始めて10年に満たないころで、どのような木造建築をつくっていくべきなのか、思い悩む日々でした。そんな折、兵庫県であの震災が起き、次々と送られてくるメディアの報道に対して、本当の姿はどうなのだろうかという疑問を胸に被災地を見て回りました。被災された人々の話をあちこちで聞きながら、時には逆に「しっかり見て勉強していって、良い家をつくってください」と励まされながら歩きました。
そこで見えてきたことは「報道で言われているほど、昔からの木造住宅は弱くない」ということでした。ただ都市部であるが故の迅速な復旧を求める声や行政指導もあって、まだ直して住むことのできるような家々が、疑問を差し挟む余地もないままに取り壊されていったようです。その後、淡路島の被災したある集落を訪れたとき、本来の漁村には似つかわしくない、新建材で張りまわしたぴかぴかの家並みが続く風景を見て、悔しささえ感じられました。

震災前までは伝統的な民家が立ち並んでいた淡路島富島の漁村風景。被震後3年、すっかり様変わりした街並み。(写真提供:金沢工業大学名誉教授、秋田県立大学名誉教授 鈴木有先生)
必要とされて一心にはたらく
コミュニティーの守り手としての大工
山古志竹沢では、工務店を営む星野勇さんに、長谷川さんが引き合わせてくださいました。まず家の中に入る前に見せていただいたのは庭の片隅につくられた仮設のお風呂。自宅前の作業小屋の横に製材機を据えて、ご自分で丸太から製材されているので、燃料としての薪は豊富にあり、震災後の復興ボランティアや、風呂に入れない地域の人々に開放するためにつくったそうです。

星野さん宅の庭につくられた仮設露天風呂
星野さんは2人の息子さんも大工をしていて、震災後からこのかた5年間、村内外の被災住宅の修復・再生に駆け回り、少しでも早く山に戻れるよう尽力されたそうです。ご自宅も一部の戸も開けたてができないぐらいに傾き、玄関横の壁にはいまだに大きな亀裂が走ったままの状況なのですが、困っている住民のために奔走するのに忙しく、自宅の工事は後回しになっています。山里というひとつの濃密な地域社会の中で大工の存在が確実に必要とされ、その期待に沿うべく一心に働くという、ある意味理想的な社会がここにあるなというのが私の印象です。
昔から大工は地域のコミュニティーにおいては、その先頭に立って祭りや祝い事を引っ張っていく役割も果たして来ました。現代社会ではコミュニティーの連帯感や一体感が少なくなり、人々のつながりが薄れていますが、天災という非常時においては、人と人とが常日頃あたりまえにつながっているという安心感が何より大事なんだなと再確認しました。そして予算など限られた条件のなかで住み慣れた家に戻れることを最優先に考え、復興の痛みを少しでもやわらげ、地域全体の再生の先導者として大工は働くのです。
私たちが訪問した少し前、星野さんたちは三宅島に赴き、災害後の復旧のあり方について交流されてきたそうです。天災は突然訪れる不幸に違いありませんが、それでもそれを新しいつながりをつくっていくチャンスに転じている星野さんたちには頭が下がります。

右から星野さん、長谷川さん、星野さんの息子の勇人さん、中村
アルチサンプロジェクトで
伝統木造住宅の再生可能性を示したい
さて、私は今、去年の特集記事にもあるように「アルチザンプロジェクト」という神戸の地震波で揺らして損傷した実験棟住宅の再生プロジェクトを進めています。この実験棟は、建築基準法上の大きな地震波に充分に耐え、またそれを超える神戸の地震波で2度揺らしても、10本ほど柱が折れたものの倒壊にはいたらないという実績をもっています。プロジェクトでは「足元を緊結していない、土壁耐力壁のみによる住宅が、地震に対して充分な耐力を発揮した」ということを発信することをひとつの目的としています。
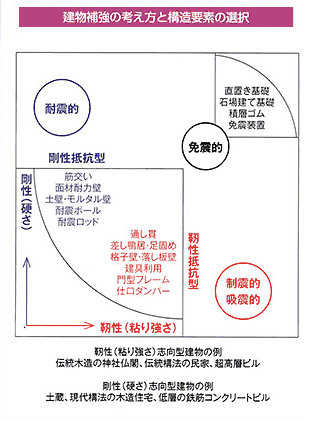
伝統木造建築は、この図表の三つの要素を上手に取り込んだ構法であると長谷川さんは説く(「地震被災建物 修復の道しるべ」より)
もうひとつの大切な意味・想いは、震災にあって倒れかかった木造住宅でも、しっかりと手を入れて修復していけば充分に再生できるんだということの証明をすることにあります。「アルチザンの家」は実験のときに入力した神戸波により、通し柱や差鴨居に取り付く柱が10本折れました。しかし、屋根をはじめ、床を構成する横架材などにはほとんど大きな損傷はなく、実験にかかわっていた私は「この実験でこの家を廃棄してしまうのはもったいない、まだ十分に再生できるじゃないか」と確信したのです。今、愛知県東郷町で再生工事の真っ只中ですが、折れた柱を差し替えて安全に修復しています。実験映像を何度も見て、どんな壊れ方をしてどこが欠点になっているかということも徐々に解かってきていますので、補強する場所や方法もおのずと解かります。「大震災に遭っても、木の家はきちんと手を入れて修復できる。」伝統構法の木の家再生プロジェクトは、命と財産を救うという意味合いを持ちながら、進んでいるのです。

たぶん中越の昔からの大工たちは、長年の経験と先人たちの仕事を見てゆく中で試行錯誤しながら、地震に耐えうる、よりよい木の家を造り出してきたに違いありません。中越の古民家に見られるようなすばらしい智恵がまだまだいたる所に存在しているはずです。そういった技術が積み重なって初めて、受け継ぐに足る新しい「伝統技術」が作られていくのだと思います。今、国では伝統木造住宅のための設計法を作ろうとしています。その設計法が、そうした全国各地に今なお息づく「伝統技術」の上に、しっかりと工学的裏づけをする方向で作られていくことを期待します。
生きることは、直すこと
私は常々「生きることは直すこと」「生きていくことは直しつづけること」だと考えています。長い人生のステージではいろいろな場面において、つまずいたり失敗したりで何かとモノやコトが壊れていきます。デジタルな大量消費社会に慣れてしまった現代では、壊れたら捨ててしまって買いなおすのがあたり前なことになってきていますが、少し前の時代までは、壊れたら修繕してまた使い続けることが普通でした。直せること、そして直せたことにこの上ない充実した喜びを感じていました。私の手元には祖父の代から受け継いでいる大工道具や、子どものころから使い続けている様々なものがあり、それらは持ち主や時を越えて思い出とともに「私の宝物」でもあります。
昔からあるいろいろなモノは「直すこと」を前提にモノづくりされていました。そこには必ず職人の存在がありました。耐用年数を過ぎたモノをどのように直したら再び使えるようになるかということを考えながら手仕事されていました。大量生産・大量消費社会の今はなかなかそういった丁寧なモノづくりがされていないように思います。いや、そうしないことが、経済成長を生んできたのかもしれません。しかし、やがて後に残るのは、使えなくなったモノたち、つまり大量のゴミであったとしたら…それはいったい、誰にとっての幸せなのでしょうか。
家も、直しながら受け継ぐもの
建物以上のものが、次世代へとつながっていく
家づくりにおいても例外ではありません。現代工法(新しい道理)でつくられる多くの住宅は、たとえば壊れたときに直していくことが難しいのが実情です。中越の民家の「コマ石」のように初めから直す時のことを見据えて造られているように、伝統的な工法(古い道理)による住宅は、容易に修復ができるように造られています。言い換えれば現代工法の家は壊れたらそれを一度まっさらに壊して新しく建て替えることが前提で造られ、伝統的な古い民家は、元の建物を壊すことなく修繕しながら100年、200年と住み続けられように造られるということです。

片岡邸の立派な茅葺き屋根。差し茅で随時修繕し、50年ほどで葺き替えていく。
その長い時間の中で、住み手は何代にも渡って家族が入れ替わっていきます。片岡さんが築200年の家を「負の遺産」と表現されていたのが印象に残っています。たしかに終わることのないメンテナンスなど手間を考えると、「受け継いでいくこと」は重荷なのかもしれません。ただその話をされる片岡さんの表情にはその言葉の裏返しで、確信と意志の強さを感じました。現代の価値観では「負の遺産」と言われてしまう民家をあえて「受け継ぎ」、次代へ「つなげる」ことで「家族という希望もまた未来につながっていく」ということを言われたんだと思います。私たちに話をされながら、横に座っているお孫さんを気づかう様子にそれがよく表れていました。
星野さんの家では、崖っぷちから曳き家をして直すという一大工事に、生きることへの執念を感じました。村じゅう総出で山から木をおろしてきて、1年以上の歳月をかけてつくり、何代にもわたって住み継がれてきた家には多くの汗と人生の記憶が詰まっています。それを断ち切ることは命を絶つことにも近いのかもしれません。生まれ育ったその地に愛着のある家を修復して踏みとどまること、支える仲間たちがそばにいること、そしてそれを可能にする古くからの知恵と技術力を持つ職人たちの存在が確かにあることが頼もしい限りです。
つくるだけでなく直せる技術をもった大工
家守り、町守りでもある大工でありたい
15年前、神戸の街を歩きながら感じていたモヤモヤが、今回の中越被災地訪問で晴れてきた感じがします。被災直後の街や家の様子にただ圧倒されて帰って来て、その後の経過は新聞ニュース報道などの情報でしか知りませんでした。今回の訪問でお世話になった長谷川さんは中越地震から5年に渡って、その後の2007年能登半島地震や中越沖地震など各地へ、中越での手ごたえをもって奔走され、相談会や設計作業を通して、親身になって「直すこと」に力を尽くされてきています。「直して使えるものは直していきましょうよ」と穏やかな技術者の目でひとりひとり訴えていくことで町並みを修復し、家を直し、人の心をも再生させてきたんだと思います。
大工として何ができるのか、何をせねばならないのか・・・。大工の星野さんのお宅で見聞したもので多くを学びました。「いや〜じゅうぶん住めるから・・」と言って笑いながらひび割れた壁や傾いた柱を説明する顔は誇りに満ちていました。大工とは単に家をつくる時だけの存在ではなく、家があり続ける間、家族が生活していく傍らでそっと見守っていて、いざという時その技術を駆使する存在なのだと感じ取りました。「家守り」と言う言葉もありますが震災のような非常時には「町守り」「村守り」となって駆け回る覚悟も必要な気がします。中越で見てきたような「直す」技術を持つ職人が必要とされるコミュニティーがあり続けることが、これからを豊かに生きる指針だと思います。
取材日:2009年8月9日・10日
取材=中村武司 取材協力=長谷川順一
撮影=石谷岳寛・山本草介 原稿編集=持留ヨハナエリザベート